※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
こんにちは、ぽっぽです。
今日の一冊はこちら↓
『残像に口紅を』筒井康隆(著)
「アメトーーク! 読書芸人」でカズレーザーさんに紹介され、話題になったこの作品。
”実験的小説”という聴き慣れない響きに興味を持ち、読んでみました。

本の概要(あらすじ)
「ずいぶん実験的な小説だね」
世界からひとつずつ、ことばが消えていく。
『あ』が消えると、『あなた』も消えてしまった。
ひとつのことばが失われたとき、はじめてそのことばがどれほど大切なものだったかがわかる。
消えていった、愛するものたち。
ことばが消滅していく世界を描いた、究極の実験的小説。
3つの特徴
世界からひとつずつ消えていく言葉たち
友人の評論家・津田得治の勧めで、主人公・佐治勝夫はある実験的なテーマを試みます。
それは、世界からひとつずつことばが消えていくというもの。
「もしひとつの言語が消滅した時、惜しまれるのは言語かイメージか。つまりは言語そのものがこの世界から少しずつ消えていくというテーマの虚構」
「ずいぶん実験的な小説だね」
『あ』が消えると『あなた』も『愛』もなくなる。
『か』が消えると『漢字』も『鏡』も『ぴかぴか』もなくなる。
ひとつ、またひとつと消えていくことばと、それが表すものたち。
もちろん地の文からもそのことばは消えています。
はじめはあまりに違和感がないため、『あ』が消えていることにも気づきませんでした。
言葉が消えれば愛するものも消える
『あ』が消えた世界では、『あなた』という妻からの呼びかけも
『ごめんなさい』や『もしもし』に変わってしまいます。
驚いたのは、ことばが消えるとその文字が含まれる人物も消えてしまうということ。
家族との食事の場面で、主人公は一人足りないことに気づきます。
ひとり消えたな。たしかにひとりいなくなった。その名とともに世界から消失した。
『ぬ』が消えた世界では、三女の絹子も消えていたのです。
実態が消えても、記憶から消滅するまでには少しばかりの猶予があります。
その残像に思いを馳せる切ないシーンが、この小説のタイトルにもなっています。
「彼女の化粧した顔を一度見たかった。では意識からまだ消えないうち、その残像に薄化粧を施し、唇に紅をさしてやろう」
まるで意地悪をされているかのように、次々と消えていく家族。
ひとつのことばが失われた時、そのことばがいかに大切なものだったかが始めてわかる。そして当然のことだが、ことばが失われた時にはそのことばが示していたものも世界から消える。そこではじめて、それが君にとっていかに大切なものだったかということが
最後に残るのは
ことばは『あ』から順番に消えていくのではなく、
ランダムに消えていきます。
実際には、著者が自分の作品にどの音の頻出度が高いかを調べた上で、
“多少意図的に”消していっているそうです。
ことばを制限されているなかで、それでも巧みな表現で対応する
主人公の様子はシュールで面白い。
最後に消える音については予想通りでしたが、
想像以上に物語としてさほど違和感なく成立していました。
ほとんどのことばが消失してからの終盤はもはや文章とは言えないものの、
最後の一音が消えるまで足掻き続ける、著者の執念が感じられます。
62 さらに「か」を引けば残る音は「い」と「が」と「た」と「ん」である
がん。がたん。がん。がん。
痛い。痛い。痛い。
本の感想
「ことばが消えていく」「実験的小説」というワードに興味を持ち、読んでみた作品です。
最初は一般的な小説に飽きたが故の、高尚な言葉遊びなのかと思いましたが、
読んでみると著者のこの設定に対する執念を感じました。
正直書かれていることを全て理解はできませんでしたが、
この作品は「ことばが消えていく」という斬新な発想と、
物語として成り立たせている著者の表現力を楽しむものかなと思いました。
そしてその点に関しては、ただただすごいとしか言いようがありません。
もし同じ発想をした人がいたとしても、実際にそれを小説にしてみようとはまず思わないですよね?
よくこんな小説を書けるな、というのが純粋な感想です。
一つ、また一つと『音』が消えていっても、
後半までは「本当に消えているの?」と疑ってしまうほど、
文章として違和感なく成り立っています。
一度目はさらさらと流すように読んでしまったので、
二度目は消えていく『音』を確かめながらじっくり読んでみようと思います。
この本の総評

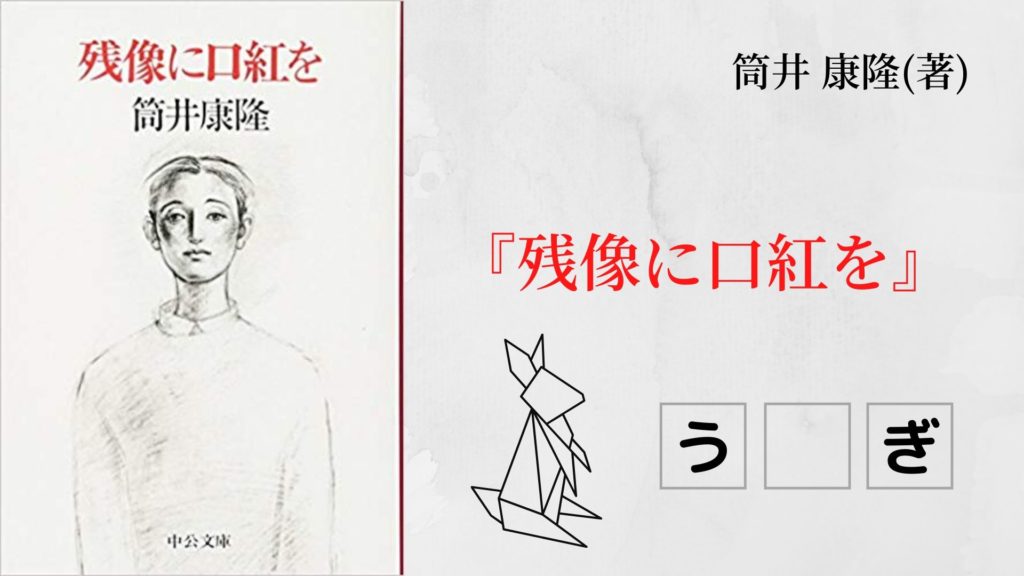



コメントを残す